縄文時代と思われる住居跡から稲わらを編んだと思われるものが発見されています。それは、現在でも見かける、わら菰(こも)に近い敷物であったのでしょう。
神話の中でも天皇や神様は、シート状のものを敷いていたとあります。
このシート状のものとは、水辺の菅(すが)であったり、動物の毛皮であったり、また藺草を織った茣蓙であったり。天皇や神様のように身分の高い人は、その敷物を何枚も積み重ねていたのです。
また、このシート状の敷物は、使わないときには嵩を低くするために丸めたり、折り重ねるなどして片付けていたと考えられます。
使う時には、重ねる。使わないときには折りたたむ。「重ねる」と「たたむ」は同じ行動を表す言葉です。日常から、「たたむもの」を命名「たたみ」としたのですね。



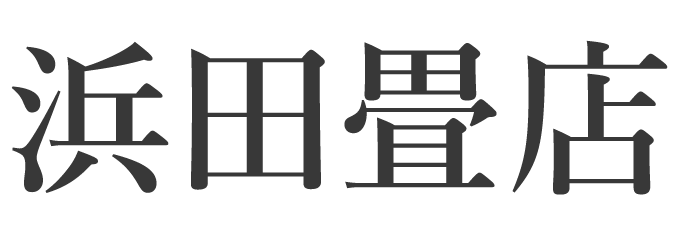

 0746-32-2371
0746-32-2371 Contact
Contact